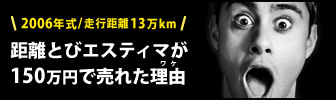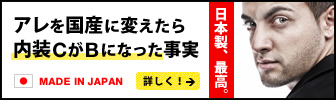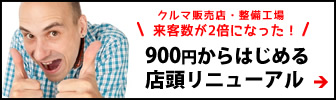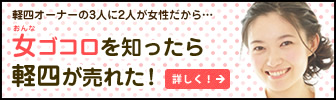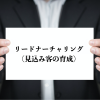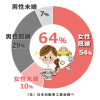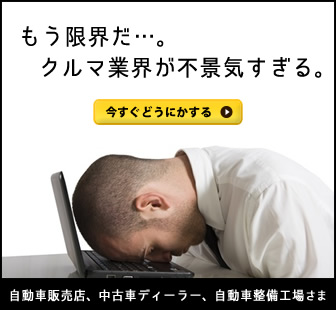活力朝礼22【野鴨の哲学】
小善は大悪に似たり、大善は非情に似たり
京セラ創業者で経営塾「盛和塾」を自ら主催する稲盛和夫さんは良く、「小善は大悪に似たり、大善は非情に似たり」という言葉をおっしゃいます。
人には優しさが必要だが、上司が部下と接するとき、部下に迎合し良い顔ばかりして甘やかすことは小善であり、これは部下達本人のためにならないばかりか会社を危うくする大悪(だいあく)である。獅子がわが子を千尋の谷に落とすように部下に厳しく接することは、非情であり薄情なようにみえるが、これが部下を育てることにつながり、立派な大善(だいぜん)である、と稲盛塾長はおっしゃいます。
部下の仕事ぶりに関して小言を言わねばならない時があります。ぶつぶつ言うのを嫌われることを恐れ言わないでいるのは小善であり大悪につながりますが、言うべきことをしっかり言うのが大善なのですが、これは非情に似てますので部下か心良く受け入れるとは限りません。
「あなたのしていることは、会社の目的である経営方針につながらない。目的である理念達成のためにはこうしてもらわなければ困る」
こう伝えることができるのは優秀なリーダー。また、部下もやって良いこと悪いことの判断基準を持つことができます。この言葉をうまく表現した逸話があります。
====================================
越冬のため南に飛び立つ渡り鳥たち(野鴨)が嵐で旅立つことが出来なかったことを可哀想に思い、湖のほとりに住む老人がえさを与えました。毎日えさをやっていると他の渡り鳥も集まり、冬をその湖で暮らす渡り鳥が増えてきました。暖かい地域へ旅立たなくても老人のえさがあるので、生きていけるのです。
こうして野鴨は南へ向かう習慣を忘れ、3年が過ぎました。
ある冬、老人は亡くなりました。
老人のあてがいぶちのご馳走に慣れ、野生をなくしてしまった鴨たちは、まるでアヒルのように肥え、羽ばたいても飛べなくなっていました。
そこへ近くの山から雪を溶かした激流がなだれ込んできました。ほかの鳥たちは丘のほうへ素早く移動しましたが、かつてたくましい野生を誇った鴨たちは、なすすべもなく激流に飲み込まれていきました。老人からのえさを目的として集まっていた渡り鳥は、全滅しました。
====================================
ここで老人が渡り鳥にえさを与えることを「小善」、この顛末を予測して与えないことを「大善」と言います。また他の例で言うと、親が子供を甘やかすのは「小善」、厳しく育てるのが「大善」だと思います。
3年次以上の先輩はただ自分の仕事をしているだけではなく「イプラらしさ」の行動規範を後輩に指導できていますか?仕事の「技術」ではなく行動指針(はきはきと元気よく挨拶、きびきび行動、お客様への心配り、提案)を伝えていますか?